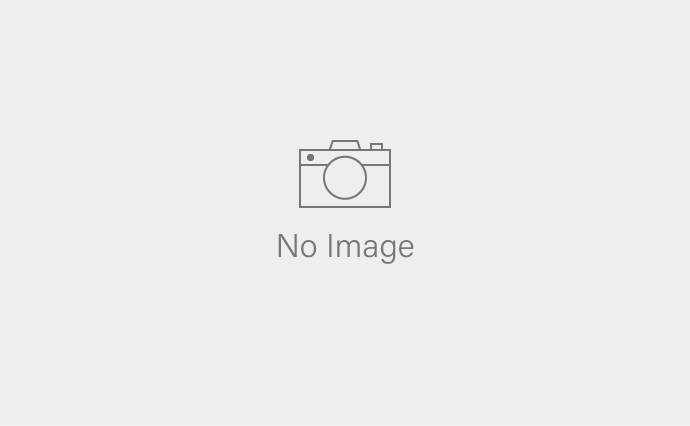― 中小企業が今知っておくべき防衛産業支援の流れ ―
① 事業者にとってのメリット
― 防衛関連ビジネスの新たなチャンス ―
「防衛生産基盤強化法」(令和5年成立)は、防衛装備品を安定的に開発・製造できる国内体制を強化するための包括的な支援法です。
この法律のもとで整備された制度を活用し認定されることで、中小・小規模事業者にも大きなメリットがあります。
主なメリット
1 基盤強化の措置
基盤の強化に資する事業者の取組(特定取組)を認定の上、直接的に経費を支払い。(サプライヤ企業も対象です。)
2 装備移転円滑化措置
装備移転のため、移動対象の装備品等の仕様・性能等を国の求めにより変更する場合に、必要な費用を助成。
3 資金の貸付け
日本政策金融公庫により、装備品等の製造等に必要な資金の貸付けを配慮。
4 製造施設等の国による保有
他の措置を講じてもなおほかに手段がないとき、国が製造施設等を取得し、事業者に管理を委託。
このように、防衛関連産業は「大企業中心」から「中堅・中小支援型」にシフトしています。
既存取引先でなくとも、部品製造・素材・ICT・電子・機械加工など民間技術を防衛用途へ転用する機会が広がっています。
② 制度の成り立ちから解説
― 「防衛力=産業力」を支える法体系の誕生 ―
かつての防衛調達は「価格・数量・納期」に重点が置かれていましたが、令和の安全保障環境では、供給の継続性・技術の維持・情報保全が最重要テーマとなっています。
これを背景に、令和5年に「防衛生産基盤強化法」が制定され、防衛大臣が基本方針を策定。以下の7つの柱に基づき、産業基盤を総合的に強化する施策が展開されています。
防衛生産基盤強化法に基づく施策等について
【主な施策】
1 基盤強化の措置
- サプライチェーン強靱化
原材料・部品の国産化、備蓄、代替素材開発などを支援 - 製造工程の効率化
AI・ロボット・3Dプリンタ導入による省力化、検査自動化、生産性向上を後押し - サイバーセキュリティ強化
米国NIST SP800-171相当の「防衛産業サイバーセキュリティ基準」への適合を支援し、電子錠設置や多要素認証など物理・論理両面で保全対策を強化 - 事業承継・技術継承支援
撤退・合併・技術移転時の設備・ライセンス・人材育成費を支援
2 装備移転円滑化
海外への装備移転時に、防衛大臣が仕様調整を認定し、助成金を交付(失注時の返還不要)
3 国による製造施設保有
災害や撤退等で生産維持が困難な場合、国が施設を取得・運営委託し、必要に応じて民間製品の製造も承認
4 サプライチェーン調査
防衛大臣は製造等事業者に対してサプライチェーン調査を行うことができる。事業者は、調査に対する回答の努力義務が定められる。
5 金融支援(長期貸付制度)
「装備品製造等基盤強化資金」により、中小事業者向けに長期・低利の公庫融資を提供。
6 秘密の保全措置
従来の契約上の守秘義務から、法律上の守秘義務にすることにより防衛産業の保全強化を図る。
これらはすべて、防衛大臣の認定や契約を通じて、法的に裏付けられた制度的支援となっています。
特に、中小企業が「計画認定」を受けることで、補助金・融資・契約支援を一体的に受けられる点が最大の特徴です。
③ 行政書士に依頼できること
― 制度活用の“橋渡し役”としての専門サポート ―
防衛生産基盤強化法関連の施策は、いずれも
「防衛装備庁への計画提出」「防衛大臣による認定」「契約書・添付資料整備」など、
精密な書類作成と省庁対応が求められます。
行政書士は、これらの手続きを中小企業に代わって次のようにサポートします。
| 支援内容 | 主な対象制度 |
| ① 認定計画書・申請書の作成支援 | 装備品安定製造等確保事業/基盤事業者認定 |
| ② 官庁照会・制度適用判断の補助 | 経産省・防衛装備庁・税関等への法令該否照会 |
| ③ サプライチェーンリスク分析 | 国産化・備蓄・代替素材開発に関する調査協力 |
| ④ サイバーセキュリティ体制文書化 | 防衛産業CS基準対応・内部規程整備支援 |
| ⑤ 補助・融資併用の設計支援 | 公庫貸付・特定取組契約の併用調整 |
| ⑥ 契約・報告・変更届対応 | 認定後の変更届・報告義務・改善計画作成 |
行政書士は、これらの制度を単発的に処理するのではなく、
「事業計画の策定 → 認定 → 契約 → 実施 → 報告」までを一貫して支援できます。
【まとめ】
防衛生産基盤強化法は、「装備をつくる力=国を守る力」という新しい発想のもと、
防衛関連産業を国家的に支える法制度です。
今後、防衛関連事業は民間技術・地域中小企業の力なくしては成り立たなくなります。
制度を正しく理解し、認定・融資・補助を適切に活用することが、
新しい防衛産業時代の成長戦略につながります。